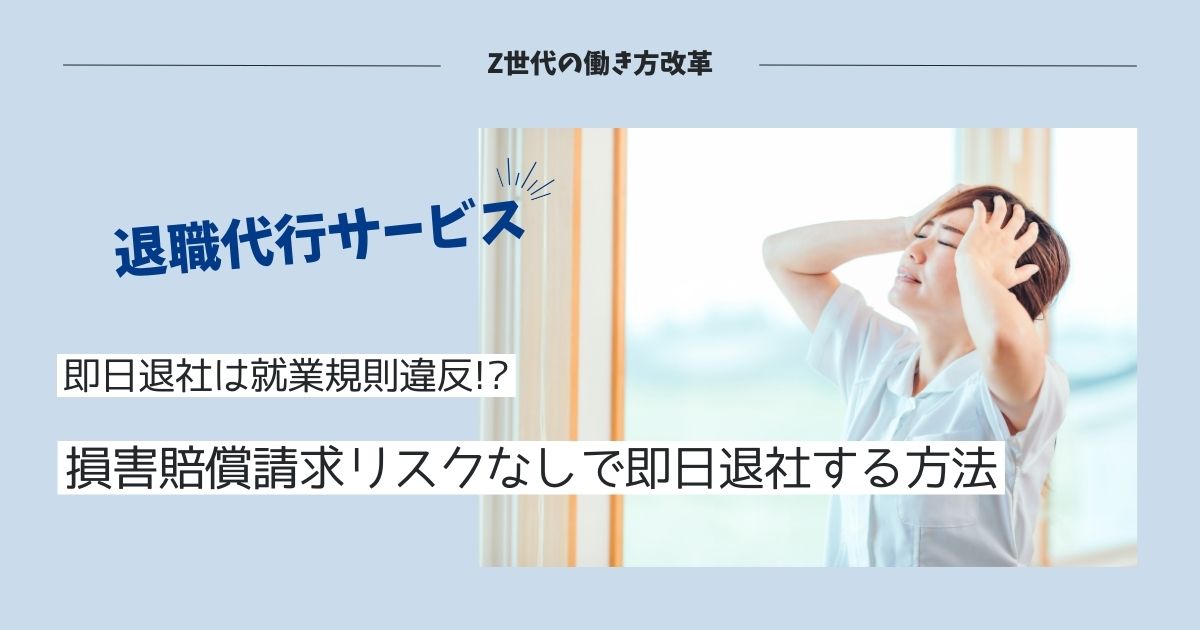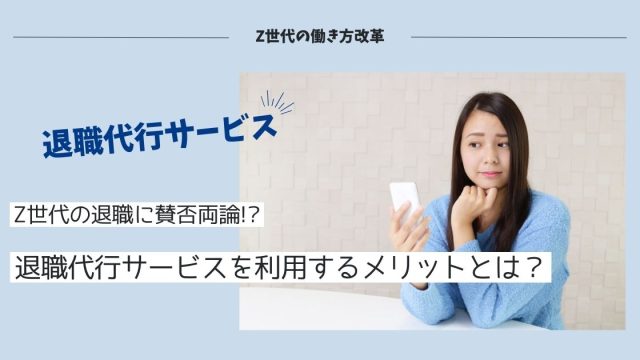「退職代行サービスを利用すると、即日退職が可能」と聞いたことがあるかもしれません。しかし、実際のところ、それは法律的に問題ないのでしょうか?違法行為に該当する可能性はないのでしょうか?
また、上司に相談せずに退職代行を利用して一方的に退職した場合、後から「損害賠償請求」を受けるリスクがあるのではと不安に感じている方も多いでしょう。
結論から言えば、適切な条件を満たしていれば、退職代行を利用して即日退職することは違法ではなく、損害賠償請求を受けるリスクもほとんどありません。
問題なく退職退職できるケース
- すでに退職の意思を上司に相談したにも関わらず認めてもらえなかった
- 消化できていない有給休暇が残っている
- 妊娠・育児・出産・介護などの理由で退職せざるを得ない
- 給料未払い、過度な残業時間、パワハラなどを受けた
※例外として、芸能人やプロスポーツ選手のような一般的な雇用形態とな弧となる特殊なケースの場合、膨大な損害賠償が請求されることもあるようです。
本記事では、退職代行サービスを利用する際の法律的なポイントや、即日退職が認められるケース、そして損害賠償請求のリスクを回避する方法について詳しく解説します。
退職代行サービスで即日退職は違法?損害賠償請求のリスクはある?
退職を考える際、まず気になるのが就業規則ではないでしょうか。
例えば、「退職を希望する場合は3カ月前までに申告すること」といったルールがある会社も少なくありません。そのため、「就業規則で定められている以上、即日退職はできないのでは?」と不安に思う方もいるでしょう。
就業規則より法律が優先される
結論から言えば、就業規則は法律ではなく、あくまで企業が定めた内部ルールに過ぎません。そのため、就業規則に違反したとしても、違法行為にはなりません。
ただし、民法では、「退職日の2週間前に退職する意思を雇用主に伝えなければならない」と定められています(民法627条1項)。
以下のご参照ください。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する
引用:民法627条1項
では、民法で定められた「2週間前の通告」というルールを守らず、退職代行サービスを利用して即日退職した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
特に、契約社員のように契約期間が定められている雇用契約では注意が必要です。
-
正社員・アルバイトの場合
→ 民法627条1項に基づき、「退職の2週間前までに意思を示せば退職可能」とされています。 -
契約社員の場合
→ 民法628条により、「原則として契約期間が満了するまで退職できない」と定められています。したがって、契約期間内の一方的な退職は損害賠償請求のリスクがあるため、慎重に対応する必要があります。
ただし、契約社員であっても「やむを得ない事由」がある場合には、即日退職が認められるケースもあります。
以下をご参照ください。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法628条
上記の民法628条にするされている“やむを得ない事由”とは、どういうものなのでしょうか。
その内容によっては即日契約解除、つまり、契約社員でも即日退職ができることになります。
契約社員でも即日退職が可能なケースとは?
契約社員であっても、特定の条件を満たせば即日退職が認められることがあります。これは、民法628条に定められた「やむを得ない事由」に該当する場合です。
契約社員でも即日退職できるケース
- 妊娠・出産・育児・介護などの個人的にやむを得ない事情
- 給料の未払い、残業代未払い、過度な残業時間、パワハラなどの会社側に落ち度がある場合
そのため、実質的に損害賠償請求のリスクは極めて低いと言えます。
会社が損害賠償請求を行うのは難しい
そもそも、企業が退職者に対して損害賠償請求を行うには、「退職によって具体的な損害が発生したこと」を証明する必要があります。
しかし、一般的に考えて、契約社員が1人退職したことで企業が計上できるほどの具体的な損害額を算出するのは極めて困難です。
したがって、契約社員であっても、適切な理由があれば即日退職は十分に可能であり、損害賠償請求を受けるリスクも低いといえるでしょう。
退職代行サービスを利用した後の損害賠償リスクを回避する方法
退職を考えている方の中には、次のような状況にある方もいるかもしれません。
先にお伝えした通り、民法627条1項では「退職日の2週間前に退職を伝えなければならない」とされているため、原則、2週間前までに退職希望の意思表明が必要になり、それを怠ると損害賠償請求されるリスクが残ります。
つまり、会社側としては退職した労働者に対して業務の引継ぎなどを怠ったことにより不利益(損害)が発生したとして、損害賠償請求をすることができます。
しかし、以下の場合は、退職者が損害賠償請求されるリスクがなくなります。
正社員でも即日退職できるケース
- すでに退職希望の意思は上司に相談しているが、認めてもらえなかった
- 消化していない有給休暇が2週間以上残っている
例えば、上司に退職を希望する旨を伝えたにも関わらず「考え直せ」「今は忙しい時期だから無理だ」などの理由で掛け合ってもらえない場合でも、民法上は「雇用契約の解除の申し入れをした」とされ、その日から2週間経過していれば退職することができます。
つまり、“退職の意思”さえ伝えればOKってことです。
さらに、正社員で働く多くの人は、消化できていない有給休暇が2週間以上残っているケースがほとんどです。
ちなみに、退職代行サービスを利用して会社に退職の意思を伝えたとしても、民法627条1項に定められている通り、その日から2週間は退職することができないため、その後も出社する義務があり即日退職することは民法上は許されることではありません。
しかし、この時点で消化できていない有給があれば、その日から2週間を有給休暇により消化することで、即日退職することが可能になります。
有給休暇を取ることは労働者の権利であるため、法律上、労働者が希望する有給消化を会社側(雇用者)が拒否することはできません。
※よくある例として、今は忙しい時期だから有給を取ることは認められないという会社都合で有給が取れないというケースがありますが、法律上、会社側が労働者の有給取得希望を拒否することはできません。
つまり、業務の引継ぎなどの理由を口実に出社を求められても、有給消化を希望することで退職希望者は出社を拒否することができる(応じる義務はない)ことになります。
結論、正社員であっても即日退社できるし、損害賠償を請求されるリスクはありません。
まとめ:退職代行サービスの利用は違法ではない!損害賠償リスクもほぼゼロ
退職代行サービスを利用して一方的に退職したとしても、違法には当たらず、損害賠償請求を受けるリスクも極めて低いと考えられます。
ただし、安心して即日退職するためには、以下の条件を満たしているかを確認することが重要です。
即日退職が認められるケース
- すでに退職の意思を上司に伝えたが、拒否されている
- 未消化の有給休暇が残っている
- 妊娠・育児・出産・介護など、やむを得ない事情がある
- 給与未払い、長時間労働、パワハラなどの会社側に問題がある
退職代行サービスは、ブラック企業や職場のトラブルに悩んでいる方にとって、有効な解決策の一つとなるでしょう。無理に働き続けることなく、適切な方法で退職することを検討してみてください。